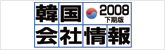ドキュメンタリー映画「自転車でいこう」が間もなく公開になる。舞台は在日コリアンが多く居住する大阪市生野区で、知的障害のある青年、李復明(リ・プーミョン)〔写真:前列左から2人目〕と彼を取り巻く街の人々のストレートな付き合いを追いかけた映画だ。杉本信昭監督に文章を寄せてもらった。
李くんとの出会いは偶然だった。6年前、生野区内にある健常児と障害児を一緒に保育する療育施設の映画を作りたいという以来を受け、私は初めてこの街にやってきた。そして数ヶ月後、この映画の企画は頓挫した。理由は何人かの障害児の母親がこどもの撮影を拒否したためだった。当時の私にはそれを覆す言葉は無かった。
2002年5月、私は療育施設の人から紹介され学童保育所“じゃがいもこどもの家”へ遊びに行った。そこへ李くんがやってきたのだ。彼は私を見るなり「家、ドコ―?」と質問してきた。李くんは初対面の私との距離を瞬く間に縮めてしまった。それは驚くべきコミュニケーションの力、技術、才能に思えた。
頓挫していた映画作りが別の形でスタートした。スタッフと私は中古自転車屋で自転車を買い、李くんを追って街を走り出した。私達は、知的障害者であり、在日コリアンであり、20歳の青年である李くんという個人を通して生野という街を見た。そしてあることに気付いた。李くんは様々な人に話し掛け時々怒られもするのだが、無視されるという事がまったくない。人々は必ず李くんに反応した。
例えば李くんの繰り出す質問に漏れなく全部答え切った高さんという女性。彼女は、李くんがたまたま飛び込んだ喫茶店のお客だったに過ぎない。初対面の二人はすぐに話し始めた。質問し続ける李くんのエネルギーも相当なものだったが、答える高さんのエネルギーはそれを上回っていた。2人のやり取りを聞きながら、私は「人の付き合いとはこういうものだったなぁ」と妙に感動してしまった。逃げずに、近くで、素直に…人間関係の原型のようなものがこの街には息づいている気がした。
そして李くんのお母さん、盧さんが登場する。彼女は28年前に光州からやってきた。在日コリアンのお父さんとの間に二人のこどもがいる。盧さん本人の撮影を申し出ると、盧さんは毅然とした態度で拒否した。通りすがりの得体の知れない人間に簡単に心を許さないのはむしろ当然に思えた。私はどうやったら盧さんとの距離が縮まるのかを考えた。しかし妙案は思いつかなかった。
そのうちに撮影の経済的な理由で、街の真ん中にアパートを借りなければならなくなったた。家賃2万5000円、日当たりゼロ。撮影の間だけとはいえ私はそこで暮らし始めた。朝早く起きて近所の喫茶店へ行き、続々とやってくるお婆ちゃん達の間でモーニングを食べてから撮影に出かける…という日常が出来上がった。
そうやってみると、驚いたことに生野の街がどんどんこちらに近寄ってくるように思えた。例えば街を俯瞰で撮影したくて、ある家に屋上を使わせて欲しいと頼みに行くと、「普通だったら使わせないけど、兄ちゃん最近よー見かけるからいいよ」とすんなりOKになったり…。そのうちに断固として撮影を断っていた盧さんが、インタビューに応じてくれた。「あんまりしつこく頼むから」と言いながら、彼女は2日間6時間に渡るインタビューに堂々と答え、おまけにスタッフに晩御飯をごちそうしてくれた。あなたたちを信用する、といおう盧さんの気持ちがひしひしと伝わってきた。
生野の街の在日コリアンは多くの困難を乗り越えてきたはずだ。だからこそ彼等には静かな寛容さがある。そして人と付き合うための厳しい知恵がある。私は、彼等こそ本当の意味の『大人』だと思う。映画「自転車でいこう」はこういう人々の懐でできあがった。撮影が終わったことを告げると李くんはこう言った。「もう遊ばへんの?」。私達は李くんに遊ばれていた…それでいいと思っている。
◆ 主な上映日程 ◆
東京 = 12月6日~、ポレポレ東中野
大阪・生野 = 来年2月7日、KCC会館
大阪 = 来年1月31日~、第七藝術劇場
名古屋 = 来年2月21日~、シネマスコーレ
TEL : 03・3303・9871(モンタージュ)