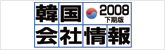私どもの劇団青年劇場は昨秋、三浦綾子=原作による「銃口」の韓国公演を行った。それ以前にも、日本では、朝鮮人従軍慰安婦の問題を扱った「椰子の実の歌がきこえる」「鮮やかな朝」に加え、「カムサハムニダ」を上演しているし、「17才のオルゴール」のソウル公演を行なうなど、韓国との関係をかなり大切にしてきた。
しかし、昨秋の公演がそれ以上にインパクトを私たちに与えたとすれば、民主化以降の韓国の変化によって、私たちが韓国現代史の様々な事実に初めて正面から向き合うことになったという感がある。
本紙にも昨秋の旅がスタートした時点で寄稿させて頂いたが、その時点で書いたことは、弾圧や拷問に対する共感の強さだった。いわば日韓の民衆レベルでの理解の共有の可能性をどう考えるのかということだったと思う。それは、靖国問題で言われるA級戦犯の問題にも共通するのかも知れない。戦争責任、責任者を明確にしたときに、民衆レベルでの交流はより深まるという政治的理解でもある。
しかし、それはまだ侵略者側の論理でもある。民衆レベルでの侵略者の犯罪に対する記憶はそのことで解消されないからだ。私たちが韓国で感じたものは、その民衆レベルの日本軍、朝鮮総督府への記憶をどれだけ自らのものと出来るのかという課題である。しかも、それは解放前の出来事に止まらないということを思い知らされ、もう一つの宿題として背負わされた。つまり戦後の韓国史に対する理解である。
私たちの理解は、韓国は米軍の存在の下に、軍事独裁政権が長く続き、その意味では「暗黒の時代」が続いていたということでしかなかった。
しかし、その政権構造にどれだけ戦前の日本支配が暗い影を落としていたのか、特に戦争責任、日本への戦争協力問題や、戦争犯罪被害者に対する補償問題が曖昧にされてきたことなどについて、戦後の日韓関係のいびつさとの関係で捉え直さざるを得ない。日本の民衆は、その歴史に対してどのように向うべきなのか。
そのようなプロセスの中で、今回の「族譜」上演が検討され、準備された。梶山季之氏の「族譜」は、氏の一連の朝鮮小説の一つとして文庫版でも出版されてはいるが、国内でそれほど知られたものではない。しかし、韓国では1978年に映画化されるなどもあって、かなり多くの人が知っていた。
私たちの心をひきつけたのは、日本の韓国統治政策として行なわれた創氏改名政策を真正面から描いた作品であることだ。創始改名の説得にあたる若い日本人画家と親日家の地主が、絵を媒介にした心の交流を持ちながらも、その野蛮な政策が強引に推し進められたことで周囲を悲劇に巻き込み、最後にはその地主を自殺に追い込んでいくというこの物語が、今、問われている歴史認識を深める上でも大きな意味を持つと考えたからだ。
主人公である若い画家は、創氏改名に納得できなくともとりあえず権力者の意向に従わなければ、大きな損失を生むことを強調する。その姿は、イラク戦争に何の根拠がなくとも、とにかくアメリカの意向に従わなければ、今後の国際的な地位が保たれないと主張するこの国の政治指導者の姿に重なる。しかし、その現実主義的な対応が、相手方に理解不能な溝と傷を作り出す。その不信の記憶は、そう簡単に消え去るものではない。そのことを歴史の中で学び直すのは、やはり今でなければならないと思う。
今回の「族譜」の上演は、韓国併合時に日本が、日本人が何をしたのかを、韓国民衆の立場に立って、もう忘れかけているかに見える現代の日本人に語り伝えるという課題を背負っている。日本人が韓国人を演ずることや、伝統芸能を表現することなど様々な困難はあるが、私たちの思いがそこにあることをこの場を借りて記したい。
ふくしま・あきお 1953年東京生まれ。東京大学法学部卒。現在(社)日本劇団協議会常務理事、青年劇場代表。
■青年劇場公演「族譜」■
10月27日~11月5日=紀伊國屋サザンシアター
11月6日=府中の森芸術劇場ふるさとホール
11月7日=かめありリリオホール
一般前売り4,935円、当日315円増。
℡03・3352・7200(青年劇場)