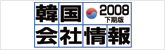韓国で2008年11月に刊行された女性作家、申京淑さんの長編「母をお願い」が、日本でもこのほど翻訳・出版(集英社文庫)された。ソウル上京の際に失踪してしまった年老いた母を探す家族の物語で、韓国では185万部超の大ベストセラーとなり、米国でも初版10万部、NYタイムズのベストセラー14位に入るなど各国で話題となっている。来日した申さんに話を聞いた。
――「母さんの行方がわからなくなって一週間目だ」の出だしが印象的だ。淡々とした文章と家族それぞれの独白による構成も巧みだ。
母というもっとも大切な存在がある日突然いなくなり、家族は強い葛藤を経験する。各章ごとに娘、息子、父親(夫)が母を思い出すわけだが、それぞれの立場から母の姿を復元したかったし、それによってさまざまな立場の読者が母の存在を感じてもらうようにしたかった。また一歩離れて母を見ることで、母をより深く理解できると考えた。そのために淡々と表現する必要があった。
――字の読めない年老いた母という設定だが。
昔の女性たちは教育を受けるチャンスがなく、字が読めない女性も珍しくなかった。文字が読めないため母はソウルで道に迷い行方不明となる。また母と娘が理解しあうのにも、字が読める娘と読めない母の違いは大きい。
私は農村出身だが、母は農作業をしながら私を含む6人の子どもたちを育て教育するために人生をささげた。今は子育てが終わり、農村で静かに老後を過ごしている。母は大地のような人であり存在だ。
――母親の料理や農作業、長男が大切にされる話など、韓国の原風景を感じさせる。
ここで描かれる母の時代の農村風景は私もよく覚えている光景だ。この作品では長男は50代か60代の設定だ。この世代の長男は家庭を守り兄弟を助けてきた。そういうプレッシャーの中で成長した。また母親にとっては初めての子どもだ。昔は家族で食事をするとき、父か長男が箸を取るまでみんな待った。長男は大切にされたが、それは重い責任を持っていたからだ。
――貧富格差、都市と農村の問題、孤独など現代社会の抱える問題が多数出てくるが。
植民地支配、韓国戦争、南北分断など韓国社会は大きな問題が次から次へと起きたので、一つ一つの事例を検証することもなく突っ走ってきた。しかしそれはどの国でも起こる問題だ。生まれ故郷を離れざるを得ない人たちも世界中にいる。また、いまは核家族化してシングル世帯も増えている。
韓国は文化や風俗が大きく変化するなかで、変わってはいけないものも変わってしまった。いまは経済的に豊かにはなったが、孤独な人が増えている。それは失ったものが多いからだろう。いまこそ内面を振り返る時間が必要だ。
――国内外で反響が大きかったことをどう考えているか。
今回、私がこの小説を書いたのは、人々の関係が暗闇の中に置かれているような状況、言葉が通じず断絶しているような社会状況だからだ。
他者の痛みに対する共感を持ち、一人一人が「母」の慈しみを持って他人に接すれば、社会が良くなるはずだ。社会全体が母性を取り戻すことが大切だと考えたのが、執筆のきっかけだ。
この作品が国内外で評価されたのは、読者がそれぞれの母を思い出し、母という存在を取り戻したい気持ちがあったのだろう。殺伐とした時代だからこそ、こういう作品が求められたと思う。
――翻訳された故・安宇植さんについて。
安先生と最初に会ったのは95年、日韓文学シンポジウムのときだ。その後、私の短編や「離れ部屋」などを翻訳してくれた。物静かだが韓国文学を日本に届ける情熱と使命感を持った人だった。研究熱心で、韓国の地方の方言なども、その地方を訪ねて調べたと聞いて驚いたことがある。本当に大切な翻訳家を失った。
――日本と在日の読者にメッセージを。
文学は、他の芸術分野に比べて伝わるのに時間がかかる。文字だけで異文化と出会うのは地味な作業だし、読む人の努力も必要だからだ。しかし異文化を深く理解するには文学作品が必要だ。この作品も絆をテーマにしている。人のつながり、家族のつながりを取り戻すきっかけとして読んでくれればうれしい。
■母をお願い■
ソウル駅で行方不明になった母。目撃情報からは母らしき人物の哀れな姿も浮かびあがるが、それ以上の手がかりはつかめない。家族は当たり前のように母から注がれていた愛情と、自分の人生にかまけて母を二の次にしていたことに気づき、母の不在によって初めてその存在の大きさに思い至る。長兄と長女、夫、失踪した母親自身の視線から再生されるそれぞれの人生と無垢の愛を描く。翻訳は故・安宇植氏。