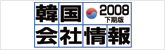パノラマのように広がる連峰
北朝鮮が世界に誇る名勝・金剛山。10月20日から在日韓国人と日本人にも開放されるのに先立って、韓国人観光客とともに3泊4日の取材ツアーに参加した。金剛山開発を進める現代グループが昨年導入したばかりの2万㌧級の豪華客船「現代楓嶽号」(ヒョンデポンアックホ)に乗って、期待に胸躍らせての船旅だ。そこには素晴らしい自然があり、現地の「案内員」らを通じて、ほんの一端だが北朝鮮の素顔を垣間見ることもできた。年配の韓国人観光客が「百聞は一見に如かず」と言ったが、その言葉どおりの旅だった。
釜山の港のはずれにある多大浦港。これまで使われていなかったが、金剛山ツアーのため整備し直した。釜山ロッテホテルからタクシーを飛ばして50分ほどかかった。私たちを乗せた満員の「楓嶽号」(乗客定員656人)は、最高20ノットの速度で北上、半日以上かけて翌日の早朝に金剛山の玄関口、長箭(チャンジョン)港に到着した。
すでに東海港からきた別の船が停泊していた。そのすぐ横には10月1日オープンしたばかりの白亜の大きな海上ホテルが目に入ってきた。現代が観光客の増大を見込んで建設した最新ホテルだ。船を降り、バスでほんの1、2分で出入国管理事務所に着いた。入国審査では、特に撮影機材に対して厳しいチェックがあり、特にカメラのレンズは160㍉までに制限されていた。持参した200㍉は船中に残すしかなかった。携帯電話や録音機も持ち込めない。双眼鏡も10倍以下でないとダメだ。
韓国旗と米国旗のデザインの服も持ち込めない。登山帽につけている太極旗のバッチを外すかどうか言い合っている夫婦もいた。「前回来たときは大丈夫だった」という夫に妻は「でも問題にならないように」と強行に主張、夫が折れた。これから日本からも観光客が訪れることになるが、注意が必要だと思った。
手続きを済ませ、表に出ると、北朝鮮の案内員が出迎えていて、20代の若い女性案内員の知的な笑顔は印象に残った。港のすぐ目の前に迫る山並みが圧巻だ。「韓国にも雪岳山、五台山などの名山があるが、金剛山にはくらぶべくもない」と韓国人客が話すだけのことはある。残念ながら港一帯は軍事施設があるとの理由で撮影は一切禁止されているので、この素晴らしい景観は撮ることができなかった。早く解禁されることを期待したい。
目の前にパノラマのように広がる幾層もの連峰は千の仏の顔をしていることから千仏台の名がある。金剛山観光が始まった98年11月からここに詰めている現代峨山の関係者が教えてくれた。冬になれば、雪で真っ白になり、また素晴らしい景観が繰り広げられるという。緯度の割に意外に温暖で、冬でも最高気温は10度にまで上がる。今回、厚着を用意してきたが、最高気温が20度にもなり、登山をすればむしろ汗だくになる。結局使わずじまいだった。
全員が入国審査を終え、21台の大型バスを連ねて、金剛山登山の出発点温井里に向かう。ここには食堂・休憩所、土産販売店、平壌巧芸団公演が見られる文化会館があり、しばしの鋭気を養える。聞けば、バスの運転手は全員が中国・延辺からきた朝鮮族だった。当地で無用なトラブルが起きないようにするための配慮だと聞いた。朝鮮族の運転手は70人にのぼり、毎日ル回転しているという。東海港からくる金剛号、東莱号、快速艇のスタークルーズ号を合わせ4隻が入れ替わりに入港するのだから、休む暇もないのだろう。
初日は、金剛山観光で全員が参加する九龍瀑布(滝)コース。いざ出発だ。
私たちの一行は、NHK、朝日新聞など日本のメディアと在日3紙の記者、現代商船ジャパンの森雅夫クルーズチーム長の総勢15人。現地で現代峨山の金義中さんと慶州観光大学出のガイドがエスコート。2人とも日本ができ、親切に説明していた。旅行を通じて感じたのだが、船中でもそうだが、食堂の係員をはじめ現代関係者がとても親切に接しているのが強く印象に残る。現代が総力を傾けて取り組んでいる金剛山開発事業であり、粗相があってはならない、と教育を徹底しているのだろう。ともかく、気持ちのいい応対は理由の別は関係なく、いいものである。
この金剛山地域で生まれた鄭周永氏。一代で韓国最大の財閥、現代グループを育て上げた彼の悲願もここにある。鄭周永氏が金剛山開発ののため北朝鮮を訪問したのは、もう十数年前のことになるが、当時は情勢が熟していず実現しなかった。いまは金剛山観光のため韓国からすでに30万人もの人が訪れており、世界にも開放される。現代はその金剛山の独占開発権を獲得した。
やれ、登山をする段になって、ふとこんなことが頭をかすめた。私たちが金剛山観光をするのはどんな意義があるのか。折りしも、南北頂上会談が実現し、北朝鮮は米国、日本との国交正常化にも本格的に動き出した感がある。なぜか、平和を誘う旅のようにも感じられた。(金時文)