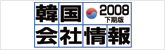◆対岸の火事ではない半島情勢◆
今号からは、韓半島情勢の現状と展望を考察する。2016年1月6日北朝鮮の4度目の核実験と2月7日弾道ミサイル技術を使ったロケット発射を受け、3月2日に国連安全保障理事会が採択した対北朝鮮制裁決議第2270号以降、韓半島の緊張が高まっている。今回の国連安保理の対北朝鮮制裁決議第2270号の特徴と緊張高まる韓半島情勢の現状について分析する。特徴の1つは、制裁内容が貨物検査の義務付け、航空機燃料の輸出禁止、北朝鮮産鉱物(金・チタン・レアアース・石炭・鉄鉱石)の輸入禁止、金融取引の禁止などとなっており、これまで7回の制裁の中で最も厳しいものであること。但し金融取引の禁止は、金正恩朝鮮労働党委員長と妹の金与正氏を指定していない。これは、北朝鮮との最小限の対話の余地を残したと推測される。2つ目は、制裁により北朝鮮住民に被害が出ないように配慮したこと。3つ目は、制裁決議を採択するまでに57日間というこれまでで最も長い時間がかかったこと。
4つ目は、対北朝鮮制裁決議を主導したのは、中国と米国であること。中国の王毅外相と米国のケリー国務長官は、お互いの国を往来して会談(1月27日北京、2月12日ミュンヘン、2月23日ワシントン)と電話会談(1月7日、3月9日)を行った。また、習近平主席と朴槿惠大統領が、電話会談(2月5日)。さらに、習主席とオバマ大統領が、電話会談(2月6日)した。中国の国家主席が、北朝鮮の核実験対応に関して米国の首脳と電話会談を行ったのは今回が初めてであった。
対北朝鮮制裁決議を主導した米中の交渉過程をもう少し細かく見てみる。中国は、早い段階から戦略的な方針を定めて動いたと見られる。1月7日王穀外相は、ケリー長官との電話会談で「速やかで強力な制裁の推進、非核化と平和体制への転換の並行、北朝鮮の核凍結は根本的な解決策ではないものの臨時的な措置として重要、北朝鮮が問題の原因は米国の対北朝鮮敵対政策にあると数回言及したという事実を注意喚起、中国は制裁に同意するが北朝鮮住民の福祉・生活に害を及ぼしてはならない」と述べた。中国のこのような方針は、安保理決議案の協議過程のみならず、決議第2270号の採択後も一貫して強調されている。
一方、米国は、米中が主導して制裁を決議したと演出したものの、実質的には中国に頼ったと言わざるを得ない。その理由は、米国は、北朝鮮に対して「戦略的沈黙政策」(発言すれば内心を見せることになるので言葉すら出さない)を取っていたからである。また、韓日の対立が、北朝鮮を利することになるのでこの韓日問題の解決を優先させたかったからである。北朝鮮の4度目核実験の翌日である1月7日オバマ大統領は、朴大統領との電話会談で「米国の韓国防衛に関する公約に揺るぎはない」という「確約」を通じ、米国の核の傘に対する韓国の疑念を解消しようとし、旧日本軍の慰安婦問題を巡る韓国と日本の合意は「正義の結果」であり、「北朝鮮の核実験という共同の挑戦に対する日米韓の対応能力を強化するもの」と述べた。この発言の意図は、北朝鮮の核実験への対応過程で韓国の北朝鮮に対する軍事対応や核武装への誘惑など「独自の軍事行動」を制御すること。また、15年12月28日の「韓日合意」を評価すること。合意に至った背景の一つに、オバマ大統領が仲介して実現した韓日首脳会談(14年3月、16年3月)が挙げられる。さらに、韓日米3カ国の安全保障協力、特に韓日軍事協力の強化を図ることであったと考えられる。
次に緊張高まる韓半島情勢の現状を分析する。北朝鮮は、対北朝鮮制裁決議第2270号に対して政府代弁人声明を発表し、「米国をはじめとする大国」との表現を使って中国とロシアに対する不満も漏らしながら「核と経済の並進路線」を通じ「自衛的な核抑止力」を強化するとの意思表明をした。また、3月2日制裁決議の採択後3月7日~4月30日に実施された米韓合同軍事演習を巡る南北の攻防が、激しさを増した。北朝鮮が核実験の臨時中止との交換を提案した米韓合同軍事演習は、中止するどころか、歴代最大規模で実施された。この軍事演習には、韓国軍29万人と沖縄駐留の海兵隊を含む米軍約1万5000人、合計約32万人が参加したが、この数は例年の約2倍の規模であった。
つづきは本紙へ