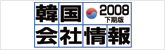洗礼名はロイス。ピアニストとして活動する傍ら、「平和と人権」をテーマに各地で積極的に講演活動も行っている。この間、演奏活動で取り上げているのが「祖国を追われた作曲家たち」だ。
「祖国を奪われた音楽家の曲には、喪失感、孤独、深い悲しみが秘められている。だからこそ聴衆に感銘を与えている。彼らの人生、その楽曲を知ることで音楽への確信を持ったし、それを人に伝えたいと思った」
崔さんは在日1世の父(故崔昌華牧師)と2世の母のもとに生まれた。ピアノを習い始めたのは5歳のとき。音楽コンクールにも出場。中学生になると音大を目指すようになった。
中学2年生(14歳)のとき、他の在日と同じく、左手人差し指に黒いインクを付けて、外国人登録証に指紋を押した。以後、登録証の常時携帯と、数年後との指紋押捺が義務付けられる。
「(子ども心に)在日であることを強く意識した瞬間だった」
1980年、善愛さんが愛知県立芸術大学ピアノ科の2年生だったとき、6歳下の妹、善恵さんが指紋を押したくないと言い始めた。
家族で話し合いを持ち、「不条理でもいまは我慢するしかない」と話す善愛さんに、「友だちは押してないのに、なぜ自分だけが押さなければならないの」と、善恵さんは疑問を口にした。
その言葉を聞いて、「私は日本社会から受けた差別や屈辱に慣れてしまっているのではないか。このままではいけないのではないか」と自問した。
そして翌81年、まず父の崔昌華さんが、その一週間後に善愛さんが押捺を拒否した。指紋押捺拒否第1号となる韓宗碩さんに続く拒否で、特に善愛さんは21歳の若い女性ということもあり、マスコミの注目を集めた。
裁判の意見陳述では、「私が指紋押捺に屈辱を感じるのは、その裏に、戦争を起こし、行い、侵略した、その時の人の心を見るからです。植民地時代に日本人が韓国・朝鮮人を支配し侵略したように、今指紋によって、自分の国の持ち物のように、私たちの感情を無視し、服従させようとしていませんか」と訴えた。指紋押捺拒否運動は全国的に広がりを見せ、支援の輪も広がる。
86年に事件が起きた。米国インディアナ大学大学院に音楽留学を予定していたが、指紋押捺をしていないことを理由に日本への再入国不許可とされたのだ。
「当時、日本での音楽レッスンに行き詰まりを感じていて、あるハンガリー出身の音楽家の演奏を聴いて、ぜひその先生のもとで学びたいと思った。そして日本人でも韓国人でもない自分を見つめなおすためにも留学をしたかったので、不許可はショックだった。寝床で『明日になったら指紋を押そう』と考えたこともある。米国入国のビザ申請に行った際、福岡の米国領事に『あなたの家は日本にある。そんなあなたが日本に帰ってこられないはずない』と励まされ、留学を強行した」
善愛さんは米国留学と同時に、「再入国不許可処分取り消し訴訟」を起こした。高裁では一部勝訴したが、最高裁で敗訴。永住権を失い、14年間、180日~1年のビザを更新した。2000年、指紋押捺制度廃止とともに特別永住権を回復した。
「父は植民地時代に対抗する形での民族的アイデンティティーを大切にしていた。私は自らのアイデンティティーに対する確信がなかったので、実は父に内心で反発もしていた。米国で、名前は留学でも事実上亡命している人が世界中から来ているのを見て、自らを客観的に見つめるようになった。音楽を通して何を表現するかも、このときに心の底から考えるようになった」
「父の生き方は強烈だったが、自分が裁判の原告になって、そして敗訴して、その情熱の一部を理解できた気がした。侵略されることが、差別を受けることが、どれだけ人を傷つけるか、またその間違いを正していくことがどれだけ大変なことか。父と時代は違うが、子どもたちにより良い社会を残すため、今後も闘っていきたい」
「在日はマイノリティーとして、アウトサイダーとして生まれたがため、逆に『個』を強く自覚して生きざるを得ない。悩む分、表現活動に向いているともいえる。若者には、マイノリティーとして生きることを居心地が良いことと感じてほしい。自らのルーツを自覚することが第一歩になる。在日の組織は、社会や政府が間違ったことをしたとき、それに対してきちんと発言できる組織であってほしい」
これまでの足跡をまとめた「父とショパン」(影書房)を12月に出版予定だ。