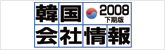日本と同様、少子高齢化が急速に進み、「多産多死」から「多産少死」を経て、「少産少死」の時代へと向かっている韓国。子どもの養育費増加、結婚や出産に対する男女の価値観の変化、出生抑制技術の普及など、社会的に出生率抑制作用が強くなるためと考えられている。韓国の人口問題について笠井信幸・アジア経済文化研究所理事に分析していただいた。
2020年になると韓国の人口増加率がマイナス0・02%と人口減少時代に突入する。そして、25年にはマイナス0・12%、30年にはマイナス0・25%まで減少すると言う。最近OECD(経済協力開発機構)がこのような予測を発表した。これまで韓国の人口問題は急速な高齢化が注目されてきたが、それに人口減少が加わると若年者の社会的扶養コストは軽くなるものの高齢化の扶養コストがますます深刻になる。こうした人口の変化は人口転換として知られている。すなわち、一国の人口動態は、経済社会の発展に伴い高出生・高死亡、つまり「多産多死」から「多産少死」を経て「少産少死」に至ると言うものである。この考え方は産業革命(1780年~1830年)を期に人口が上昇したイングランドウエールズがモデルとなり一般化された考え方である。工業化以前の伝統的農業社会では、飢饉、疫病、戦争等のために死亡率が高く、他方農業主体社会であるため、労働力確保の観点から高い出生率が維持される。その結果、近代化以前は高死亡・高出生で大きな変動を保ちつつも平均的には人口増加率(出生率―死亡率)は低い。
次に、工業化、都市化が進むと、所得水準の上昇、医学や公衆衛生の発達により、乳児死亡率などが低下し社会全体の死亡率は低下するが、出生率は依然として高水準にある。その結果、多産少死の社会が実現し人口は増加する。その後、出生率も死亡率に追いつくように低下し、少産少死段階に入る。この時代になると出生数を減らしても家族・社会の存続が可能となること、子供の養育コストの増大、結婚・出産に対する価値観の変化、出生抑制技術の普及など社会的に出生率抑制作用が強くなるためと考えられている。ちなみに、日本は明治維新以前が多産多死、明治から昭和30年代半ばまでが多産少死、昭和30年代半ば以降が少産少死の段階であると言われる。韓国も図のように少産少死段階にある。
ところで、人口転換では少産少死の段階になると人口動態は安定すると考えられていたが、最初にこの段階に達した欧米諸国において出生率が死亡率を下回る、これまでになかった現象が現れている。つまり人口数の絶対的減少局面だ。これは「第二の人口転換」と呼ばれ近年注目されており、韓国の2020年の人口増加率マイナスは、まさにこの段階に入ることを意味しているのである。しかし、最近さらに注目される局面が現れている。少子化先進国であるフランス、スウェーデンでは00年代に入り合計特殊出生率(TFR、粗再生産率)の回復が見られるのだ。これは15 歳~49歳の一人の女子が一生の間に生む平均子供数を表わし、この数値が2・08であれば親の世代と子供の世代が同数で置き換わると言う理論値で、これを下回り続けると少子化が進行し、将来的に人口が減少していく。しかし少子化先進国ではTFRが上昇しており、人口増加局面に反転しているのである。これらの国々では長い間少子化に悩まされたことからきめの細かい家族手当や保育施設などの出生インフラの構築を積極的に行ってきた。しかも重要なことはそれら施策が長期間にわたって行われてきたことで、その成果がTFRの反転・上昇となっているのである。
高齢化対策が叫ばれている韓国も、すでに出生インフラ対策に取り組まなければならない時期に入っており、その際別々に取り組む施策よりは、少子高齢化が同時進行にあることも踏まえて施設など合併可能なものはパッケージにする新扶養者対策が有効であろう。