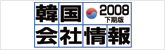拉致問題から派生して北朝鮮の現状についての報道がかまびすしい。朝のワイドショーなどは手を変え品を変え、「世界一アンビリーバブルな国」について時間を割いている。
最近の私は、どんなに興味本位な内容でも、毎朝、遅刻しそうになるまでテレビの前から離れられない。今まで見たことのない映像にくぎ付けになってしまうのは、北朝鮮に父方の叔母が住んでいるからだ。
1961年ごろ、父に抱かれて、帰国船に乗る叔母を見送っている3歳ぐらいの私の写真が残っている。私の手には紙テープがしっかり握られている。
亡くなった祖母が「五人姉妹の中で一番優しい娘だった」という叔母も帰国して40年を経て、65歳になった。祖母の存命中、父は祖母とともに、何度か祖国訪問団に混じって北朝鮮の叔母を訪ねていた。食べ物や衣類、薬など、いくつものダンボール箱を届け、祖母は愛する娘とつかの間の再会の時間を過ごした。
彼女は日本に帰ってくると言葉少なに「信子をポケットに隠して、連れて帰りたかった」と言っていた。北朝鮮に関する報道は、そんな祖母と父の思い出につながって私の涙腺をもろくする。
拉致被害者の家族の涙は、悲しい別れを経験してきた在日の無念の涙そのものだし、信じられないような北朝鮮の惨状は、同じ民族として怒りのような、苦しみのような痛みを持って胸に迫る。昔、父が「朝鮮民族は本当に不幸だ」と言っていたのをきのうの事のように思い出す。
中学生だった私は、「でも、不幸ばかりじゃない、北も南も在日も明るい未来がある」と信じたかった。
現在公開中の『夜を賭けて』という映画は、北朝鮮関係の報道で暗い気持ちになっている人にとって、一服の清涼剤になってくれるような作品である。昭和30年代の在日の姿をパワフルでエキセントリックで憎めない存在として描ききっていて、見終わった後、救われる。
貧しくても、学歴がなくても、笑いがあるし、未来もある。どこの国でもどん底のマイノリティには、ある種の神々しい明るさが垣間見える瞬間がある。最悪の情況でも人間は強く、明るくなれる。『夜を賭けて』には、見るものに勇気を与えてくれるような、そんなエッセンスがちりばめられている。
この作品とは世代が違うが、中学2年から民族学校に通った私も在日の世界にどっぷりつかり、同じ在日の友人達と同じ釜の飯を食って(寮生活だったので)中学、高校時代を過ごした。映画の登場人物と重なるような、ハチャメチャなキャラクターがいっぱいいて、とんでもない学校生活だった。でも、貧乏でも、差別されても在日の子供達はすくすくと大人になった。『夜を賭けて』の金義夫は、私の周りに生きている。
(本紙2002年12月20日号掲載)
ユン・ヤンジャ 1958年、神奈川県生まれ。在日3世。和光大学経済学部卒。女性誌記者を経て、91年に広告・出版の企画会社「ZOO・PLANNING」設立。