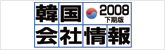日本を代表する映画監督、大島渚が1月15日に亡くなった。社会問題をテーマにした映画を撮り続け、日韓関係や在日問題についても高い関心を寄せた監督だった。門間貴志・明治学院大学准教授に寄稿「韓国をみつめ続けてきた大島渚」を寄せてもらった。
◆韓国を見つめ続けた大島渚 門間貴志(明治学院大学准教授)◆
大島渚が亡くなった。テレビの討論番組で討論する姿を憶えている人も多いだろう。しかし大島は日本のみならず世界の映画界でもっとも重要な監督の一人であった。
京都大学法学部を卒業後、松竹に入社した大島は、権力と対峙する闘争的な作品で早くから注目を浴び、松竹ヌーベルバーグの旗手と呼ばれた。
しかし大島の映画に一貫した演出スタイルと言えるものはない。固定したスタイルを拒絶し、常に新しいものに取り組んできた。彼にスタイルがあるとすれば、それは主題である。それはある種の日本人論と呼ぶこともできたであろう。
大島が日本人を描くためにしばしば合わせ鏡のように対峙させたのは韓国(朝鮮)であった。触媒と言ってもいいかもしれない。
古くは『青春残酷物語』(1960)で、主人公が韓国の学生運動を伝えるニュース映画を観る場面を入れ、当時の民主化闘争に対してさりげない共感を示していたものと思われる。松竹退社後の大島は自らのプロダクション「創造社」を設立し、活躍の場を劇映画以外の分野にも広げた。
テレビドキュメンタリー『忘れられた皇軍』(63)は大きな話題となった。カメラは日本軍人として戦地で負傷した在日韓国人たちが、日本政府の補償を求めてデモをする姿を映しだす。しかし日本国籍を保持していないという理由で役所からは門前払い。韓国政府の駐日代表部(当時はまだ国交がなかった)に行っても事態は好転しない。
デモの後の酒宴はやがて内輪もめの喧嘩となる。怒りのあまり眼鏡を外して泣く一人の元軍人。戦地の爆発で眼球を失った彼の眼から涙がこぼれるのをカメラはアップでとらえる。戦後の日本社会に対する大島の怒りがむき出しとなる。
大島はテレビのドキュメンタリー『青春の碑』の撮影のため、64年に韓国を訪れた。当初は李ラインの漁民を取材する企画だったが、局の事情で娼婦を更生させる社会事業の美談に変更された。しかしこの取材で大島は韓国に対する関心をさらに深めた。韓国映画を鑑賞し、そして鄭鎭宇ら若手映画人と会っている。
取材中に街頭で撮影した膨大な枚数の写真は、後に短編ドキュメンタリー『ユンボギの日記』(65)に結実した。韓国の貧しい少年が書いた同名の手記は、日本でも翻訳されて広く読まれた作品だが、大島の映画は手記の引用だけではなく、韓国の青年たちへの期待にあふれた言葉を託す。『日本春歌考』(67)には、紀元節の復活などに見られる当時の日本の右傾化を批判する要素も見える。しかしここには一人の在日朝鮮人の少女が登場し、従軍慰安婦の歌を歌う。主人公たちはベトナム反戦集会に参加するが、彼女の歌は新しいフォークソングと誤解され喝采を浴びる。映画の最後に女性教師が、騎馬民族説を滔々と語り、日本人の故郷は朝鮮だと高らかに宣言する。
カンヌ映画祭に招待された『絞死刑』(68)は、死刑制度と在日韓国人差別をとりあげた作品である。物語は58年の小松川事件に材をとっているが、実在の事件の冤罪を声高に主張するものではない。殺人犯として死刑判決を受けた一人の朝鮮人青年Rが、刑の執行の失敗で記憶喪失になるという衝撃的な場面で物語は始まる。心神喪失状態での刑の執行は禁じられているので、役人たちは何とかRの記憶を取り戻そうとする。
ブレヒト風のブラック・コメディーが展開され、グロテスクな日本人の姿、また祖国と日本の両方から疎外された在日の立場を描く。大島は日本人が蓋をして隠してしまいたい醜悪な部分を常に暴こうとしてきた極めて野心的な監督であった。
若い映画ファンにとって最も知名度の高い大島作品の一本である『戦場のメリークリスマス』(83)は、ヴァン・デル・ポストの小説の映画化で、第二次大戦中のジャワにあった日本軍の捕虜収容所を舞台としている。ここに大島はわざわざ原作に登場しない朝鮮人軍属の金本という人物を追加した。彼は男色の禁を犯してオランダ人捕虜と関係を持ったことをとがめられ、不条理な切腹を命じられるのである。こうした試みもまた、彼が韓国(朝鮮)という視点を導入することにずっとこだわり続けてきたユニークな存在であったことを示すものである。(大島は他に中国や沖縄も取り上げている)。
長らく日本映画の上映が禁じられていた韓国では、大衆文化開放以後、初めて大島作品が紹介され、その独特な作家性と韓国への視点において評価が高まっている。改めて大島監督を追悼したい。最後に、崔洋一監督と呉徳洙監督らが、若き日に大島の助監督を務めていたことも付け加えておこう。