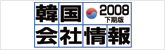◆「両国で正しい歴史認識を」◆
筆者は先日、九州の唐津市を訪れ、唐津焼陶房などを見学し陶工13代子孫、中里紀元氏と会うことができた。唐津焼にはその昔、李朝の陶工がもたらした技法が今も生き、心にしみてくる美しさがある。暮らしの器として、また、侘び茶の器としてその魅力は人々を惹きつけてやまない。
文禄・慶長の役(1592~98年)に出陣した九州の大名たちは、多数の朝鮮陶工を連行して帰国した。その技術で唐津藩内でも、多くの窯が築かれ、新しい製陶技術が導入された。その主なものをあげてみると、①割り竹式登り窯(竹を割って斜面に伏せた形で、複数の焼成室が連なり、熱効率にすぐれた合理的な窯。初期には茶の湯道具や日用の壺・皿・鉢類が生産された)②蹴ろくろ(回転軸の下についている盤を足で蹴って回す方法。回転力を足で加減しながら成形できる利点がある)などがある。
唐津市唐人町の望郷の丘へ中里紀元氏に案内された。唐人町は約400年前、秀吉の朝鮮侵略戦で連行されてきた人々の町で、陶工以外に織物工たちも大勢いて近くの川で働いていたという。ここは唐津でも海のよく見える丘で、故国の家族を思い、先祖の墓碑を建てた望郷の丘だ。この丘に御門茶盌師、八代壮平から右兵衛、藤太郎、祐太郎らの中里本家の墓地がある。前面の空の下は玄界灘の海で、その向こうが朝鮮半島である。墓碑は唐人町の人々がいまも祭祈し、守っている先祖の墓である。(中里紀元文献)
中里紀元氏は元中学校の歴史教諭で、歴史学者、評論家そして陶芸家である。奥さまが開いた「唐津焼あや窯展示場」、茶室「松友庵」や「古唐津ミニミニ資料館」が唐津市町田にあり、好評を博している。その著書に「率中記念 中里紀元展」及び「豊臣秀吉の朝鮮侵略(上下)」があり、ことに下巻に書かれている「あとがき」を筆者が読み、深い感銘を受けた。その「あとがき」の一部内容を次にあげた。
「文禄、慶長の役で唐津藩初代藩主寺沢志摩守広高によって連行されて来た朝鮮陶工又七(トウチル)が私の祖先である。私の父は長男で中里家に代々伝えられて来た「中里喜平次口上覚書」などの文書を保管し、その中に「高麗人又七」という記録があったにもかかわらず、私たち子どもに祖先が朝鮮人であるという事を一言も語ることはなかった。
私たちの祖先は朝鮮陶工たちと陶工の村、椎の峯(伊万里市府招)に故国朝鮮の神、高麗神社を建て朝鮮式の供物を捧げ、故国の舞いを踊り、江戸時代を通して、それを守り続け朝鮮人の子孫であることを隠そうとはしなかった…、しかし明治以降の征韓論とともに隣国を蔑視する政策と教育が進められると、秀吉の侵略戦争を美化する考えが再生産された…。
一方、いまは朝鮮陶工の子孫たちの多くが、胸をはって、その祖先の祖国が朝鮮であることを口にし、日本に渡来して有田や伊万里、唐津で日本の窯業史を革新的に変革させたことを誇ることを殆んどしない。それは日朝関係史の正しい研究が、まだ充分行われていないし、その成果が一般の人々に広められることなく、その結果、日本人の抱く、いままでのゆがめられた朝鮮観が改善されていないからである。佐賀県は文禄の役四百年にあたって秀吉の侵略基地名護屋に資料館を作り、この侵略戦争を日本側と朝鮮側の二つの立場に立って展示計画するとしている。この秀吉の朝鮮侵略戦に二つの立場、二つの史実はない。日本の立場であれ、朝鮮の立場であれ、秀吉の侵略戦争に変わりはないのである。史実は一つ秀吉が朝鮮の国土を荒廃させ、民衆に悲惨な状態をもたらし、自国民も苦悩させた侵略戦争であったということで、それ以外の史実はない」
まさに、中里紀元氏は稀有にみる知識人、歴史学者、評論家、博愛主義者であるといえよう。
さらに中里氏は本書上巻の「まえがき」の中で、「秀吉の侵略戦争をたたえ肯定する考えが、いまも根強くあり、両国民の、この侵略戦争に対する大きなズレは、まだ残されたままである。征韓論や日韓併合を日本国民が肯定して来たのは、秀吉の侵略戦争、文禄・慶長の役の真実が日本国民に知らされなかったことから来ている。この戦争の真実を探し、この本を記述することで、日本人の誤った、この戦争への知識、認識を正し、朝鮮の人々がもつ知識、認識と同じものをもち、理解していくようになればと思い、この本を出版した」と書いている。